基本情報

草薙神社御朱印

草薙神社拝殿・本殿
鎮座(所在地)
静岡県清水区草薙349
創祀
景行天皇53年(西暦123年)
社格等
式内社(小社) 駿河国有度郡三座並小云々草薙神社
旧社格:県社
御祭神
主祭神
日本武尊

草薙神社日本武尊像
境内摂社
北側九社
住吉社
春日社
愛宕社
白鬚社
厳島社
稲荷社
荒神社(表示が読みにくいが恐らく)
天神社
天皇社(本社のみ単独で祀られている)

草薙神社北側九社
南側九社
浅間社
山神社(表示が読みにくいが恐らく)
八幡社
子安社
○○社(表示が欠落しているが、社殿のサイズから恐らくもう一社祀られているものと思われる)
賀茂社
内宮社

草薙神社南側九社
縁起
景行天皇第二皇子の日本武尊が東国の蝦夷が叛いたので、之を平定するため吾嬬国(あずまのくに)に行く途中、この地で逆賊が起り尊を殺そうとして原野に火を放った。
尊は佩用の剣を抜いて「遠かたや、しけきかもと、もやい鎌の」と鎌で打ち払うように唱え剣を振り草を薙ぎ払ひ火を逆賊の方へなびかせ尊は無事に難を逃れた地を草薙という。
その後佩用されていた天叢雲の剣を草薙の剣と名稍を変更になり草薙神社に真剣として奉られる。
今より一八六〇余年前である。
『草薙神社 参道案内板』より
当社は何時頃の草創か、之に関する文献はないが類従国史清和天皇貞観元年正月二十六日に駿河国有渡郡草薙神社に従二位を授けられ、正拾四町の位田を下賜されました。
又歴代東夷御討征の折は必ず奉幣され尊のご冥護を祈られました。
この外、朱雀天皇天慶年中には、藤原秀郷が平将門御征伐のための奉賛がありました。
その後、今川、豊臣、徳川の諸侯には社領を奉納され、尚今川範国公には建武年中に御社殿を再建されました。近くは天正十七年徳川家康公の御社殿造営、続いて江戸時代文化七年に修理等が行わはれ、明治元年十月勅使植松少将、神祇官帯同にて御官幣を奉納されました如く、昔より皇室を始め武将名士の崇敬が厚く御神徳が高かったことを知ることができます。
『草薙神社 参拝のしおり 沿革』より
(略)その後、景行天皇が日本尊命の勲功の地を尋ねようと、景行天皇五三年(西暦123年)八月に天皇は郡郡に詔して曰く、「こいねがわくば、日本尊命の征定された国郡を巡視する。」そこで天皇は直ちに出発せられ、先ず伊勢に行幸され、次いで東国に向かはれ九月二十日に当地に御着になり尊の奮斗び後を封じて御親しく一社を建立し、日本武尊を奉祀し、御霊代として、草薙の剣を奉納されました、(中略)その後草薙の剣は第四十代天武天皇の朱鳥元年(西暦六八六年)に勅命により現在の熱田神宮に奉祀しされました。
『草薙神社 参拝のしおり 御由緒』より抜粋

草薙神社大鳥井脇案内板(由緒)

草薙神社大鳥居脇案内板(ロケット)
交通情報
公共交通機関
JR草薙駅 下車徒歩18分
車
東名高速「清水IC」より約20分
駐車場
大鳥居(日本武尊像)の道を隔てて向かい側に参拝者向け駐車場が5台程度あり
参拝記
日本武尊のゆかりの神社としてあまりに有名な「草薙」の神話の地。
国道1号線からJR東海道線と静岡鉄道清水線の線路を越え、草薙神社通りの緩やかな坂を登ってゆく。草薙神社通りに入るとすぐに「天皇原公園」という公園があり、このあたりに「天皇原」という地名が残っていることがわかる。
この天皇原は社伝にあるように西暦123年に景行天皇が日本武尊のいわば「ゆかりの地を訪ねる」巡視・行幸の旅に出た際に、この地にて宿営をしたという話があり、もともとは「天皇原」の地に元の草薙神社が鎮座していたという話もある。
面白いのは、参道正面の鳥居の右脇に「龍勢(流星)煙火について」という無形民俗文化財に指定されている「のろし」当時の「ロケット」の案内が出ていて、境内の神楽殿脇にもその実物が展示されている点である。
恐らくだが、日本武尊の草薙伝説=火からの連想で、こうした火を扱うことについて日本武尊のご加護を受けたい、という事なのだろうと想像ができる。
拝殿正面の随神門にも打上げ用の筒の展示と説明が為されている。

草薙神社神楽殿・龍勢(流星)煙火

草薙神社大鳥居脇案内板(ロケット)

草薙神社随神門・打ち上げ筒
静岡県のこのあたりにはヤマトタケル伝説がそこかしこに残されており、有度地域に20以上の伝説が伝えられているらしく、他の地域に比較しても突出して多い地域とのことである。
前述した「天皇原」についても、当時天皇の神霊を遷した「天皇社」があり、明治末年に草薙神社に合祀され、その後もこの一帯を「天皇原」と呼んでいるらしい。
本殿脇の「北側九社」の脇に「天皇社」と書かれた独立した小祠が祀られている。
草薙伝説については、この地から数キロ離れた庵原川のほとりに「久佐奈岐神社」という神社があり、昔はこちらの草薙神社に対して「東久佐奈岐神社」と呼ばれていたそうだ。
別途久佐奈岐神社の訪問記の中で記述したいのだが、こちらは西暦110年に詔勅により「日本武尊が東征の途中この地に本営を設けたとされる旧跡の地」にあるとされている。
こちらはどうやら当時の日本武尊の部下であった吉備武彦命が祀った所らしい。
草薙神社のある有度地区も、久佐奈岐神社のある庵原地区も、どちらも周辺に多くの古墳が点在し、昔のこれらの地域の中心的な地区であったのだろう。

草薙神社拝殿
日本武尊については、実在を疑う説も多いが、面白いのはやはり日本武尊伝説が残る地区がそれなりに筋だっているというか、当時の大和朝廷の影響範囲を広げていくという歴史の流れにある程度沿った形で、しかも様々な人間くさいドラマが残されていることである。
特にこの草薙伝説はその中でも極めて有名であり、誰もが日本武尊の実在性について、すこしなりとも「本当にいたんじゃないの?」とちょっと思わせる何かがある気がする。
もう一つ、これはあくまで妄想であるが、日本武尊伝説の残る地の中で、一部の地域では日本武尊を「天皇」として扱っている所もある。もしかしたら「天皇原」の起源は父の景行天皇行幸ではなく、日本武尊自体が天皇として扱われていて、伝説の故に「天皇原」になったということはないのだろうか?

草薙神社大鳥居
本殿脇に「南側九社」「北側九社」の境内摂社があるが、いくら数えてもその数にならない。
一部、社名が書かれた札が欠落していたり、薄くなっていたりして、写真を撮影して引き伸ばしてみたもののどうしても特定できず、インターネット上の情報でいくつか埋めているがそれでも九社にならないのはどうしてだろう・・・。
御朱印
社務所にて授与(2020年7月23日時点、新型コロナウィルス感染症の影響かは不明だが、書き置きのみの授与)


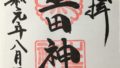

コメント